「置き本」って聞き慣れない言葉に違いなく、たぶん造語だと思います。
部屋の本棚にひっそり鎮座している本のことです。
ボクは、本を買う。
で、購入時よりほとんど手つかずの本を「置き本」と捉えています。 時には積極的に「よし、これは置き本として買おう!」という時もあったりしますが大抵は、
「おう、コイツを料理してやるぜ!」
と勇んで買った本が即刻見事に家の重力に取り込まれ、ポカーンと自分の所有欲のただ満足で忘れ去られてしまう。そんな本こそが「置き本」なのです。
で、ね。
その置き本というものは時に、ものすごい威力を発揮し、光り輝くから面白いのです。
今日はその話です。(以下敬称略)
先日内田樹の「日本辺境論」を読み、自分なりに行き着いたのが福田恆存と梅棹忠夫でした。
飽くまでなんとなくなのですが、調べていて、著作を読んでみたくなった言論者と比較文明学者でした。 この二人はどんな事を書いているのか? いますぐ読みたい。
Amazonでポチッと購入するかと思った矢先、
「いや、まてよ」と。
2メートル奥で出番を待つ本棚の棺をギギギー・・っと開けました。
あった、あった。ありました。
文藝春秋編「戦後50年 日本人の発言」に二人の著述がちゃんと、載っていたのです。
新たに買う必要なんて、全くないのデース!!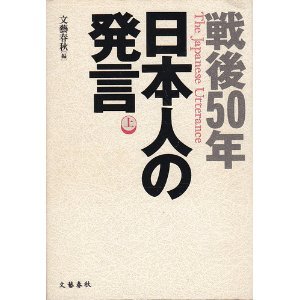
文藝春秋編「戦後50年 日本人の発言」(1995)。
これは上下巻の一大オーソリティーで、その当時に選び抜かれた論文・作品・発言が時系列で50年分編纂されています。ブックオフで4年ほど前に出会い買った本で、当時うっすら読んだのだが、喫緊の主題として触れていないため、どうしても集中力と頭に入る情報は減り、置き本と化しました。今回やっと自分の興奮と結びついてこの本のゲートがようやく開いたわけです。まずは、そのことがとても嬉しいのです。
福田恆存と梅棹忠夫。
この二人の言論者に対して、文藝春秋の編集者たちが選んだもの。
それが福田恆存「平和論の進め方についての疑問」(1954)と、梅棹忠夫「文明の生態史観序説」(1957)。 まずは福田の「平和論の進め方についての疑問」よりちょっとだけ引用します。
「一種の現代病であって『自己抹殺病』とでも名づけませうか、すべての現象や問題を、自己といふ主題から切り離し、遠ざけて扱ふ傾向です。病者はあらゆる問題から自己を排除する。それはあたかも犯罪者が証拠の指紋を拭ひとらうとするのに似てゐます。問題のどこにも自己が存在しないことを確かめ、証明しえてのち、はじめて安心するといふぐあひです。(中略)それをやれば、まづ第一に、問題は自分との直接の関係から離れます。第二に、自分ひとりだけの問題ではなくなるので荷が軽くなります。第三に、さしあたつてどうかうできる事柄ではなくなるので行為からまぬかれます。 平和論もそのひとつですが、まだこれだけの一般的診断ではかたづきません」
血しぶき。
これが昭和29年ですよ。
自己を排除する。それも指紋を拭き取る犯罪者のように・・。 この超絶メガトンパンチが後にも先にも続いているのだけど、この続きはぜひ本を手に取って確かめてほしいです。
このような強烈な言論も論壇では実りある論争にならなかったとの注釈もあり、「そして今も脈々と・・」と思いぶったまげた。まさに「日本辺境論」にも通じる、その「世界の中心」として語ることのできない病のシンクロナイズドっぷりはすごく、日本人(つーか自分)を悩ませ続けている持病だと言えます。
一方、梅棹忠夫は「文明の生態史観序説」で何を書いているか?
彼は比較文明論者として切り込みます。
「日本は文明國になつたというけれど、みんな西歐のマネじやないか、というのが、近代化の過程を通ってくる間じゆう、日本のインテリの自尊心をなやませつづけたジュモンだつた。このジュモンは、いまでも効力がある。しかし、こういう素朴な血統論は、あまり深刻に考える必要はないようだ。全體の生活様式はちやんと日本向きのパターンがつくられていて、必ずしも西歐化しているとはいえない。 わたしは、明治維新以来の日本の近代文明と、西歐の近代文明との關係を、一種の平行進化と見ている。」
彼は「ジュモン」に対してはわずか数行で片付け、世界の特性に魅せられています。
彼は、第一地域=欧米と日本の高度資本社会と、第2地域=ロシアや中国、イスラムなどの独裁体制社会とに、世界を区分してその比較を展開するのです。もう少し引用します。
「わたしたちが見て、すぐ氣がつくことは、第二地域において最近三十年間におこつた革命の數のおびただしさである。(中略) すくなくとも今まで、高度資本主義國になつた例は一つもない。そこでは、革命によつてもたらされるものは、おおむね独裁者体制である。そして革命以前の體制は、封建制ではなくて、主として専制君主制か、植民地體制である。(中略) 第二地域の歴史は、大たいにおいて、破壊と征服の歴史である。王朝は、暴力を有効に排除し得たときだけ、うまく榮える。その場合も、いつ襲いかかつてくるかもしれない新しい暴力に對して、いつでも身がまえていなければならない。それは、おびただしい生産力の浪費ではなかつたか。(中略) 第一地域の特徴は、もはやあきらかであろう。そこは、めぐまれた地域だつた。乾燥地帯のように、文明の發源地にはなりにくいが、ある程度の技術の段階に達した場合は、熱帯降雨林のような手ごわいものではない。何よりも、ここは端つこだつた。中央アジア的暴力が、ここまで及ぶことはまずなかつた。(中略) 第一地域というのは、ちやんとサクセション(遷移)が順序よく進行した地域である。そういうところでは、歴史は、主として、共同體の内部からの力による展開として理解することができる。それに對して、第二地域では、歴史はむしろ共同體の外部からの力によつて動かれさることが多い。」
とても長い引用になりましたが、梅棹氏の俯瞰的世界史観では、面白い現象が出てきます。
日本は「端つこ」で、封建体制時にぬくぬくとブルジョアが育ち、内部革命が可能だった。
一方、中国やイスラムなど文明発信地の「歴史はむしろ共同體の外部の力によつて動かされる」、と。 この解析が面白く、今の政治面や経済面でも活用できそうですが、ひいては国・地域によって様々な持病があることを暗に教えてくれています。
また、日本は自成的に共同体のサクセション(遷移)が進んだ希有な、めぐまれた国なんだよと言っています。
引用はしていませんが、梅棹忠夫は第二地域の暴力姓についてもかんたんに論じています。
この論考が秀逸で、モンゴル族研究からキャリアをはじめた梅棹氏をして「乾燥地帯は悪魔の巣だ。」という感慨を述べています。 それほど砂漠と暴力に関係性を看ているということです。
これは感想ですが、広大な砂漠では一つの花を植えよう、という小さな「まごころ」ですら育ちづらい土壌かもしれない、とボクはふと思いました。
そのヒューマニズムがその地域として意味がないことを、知り抜いているからです。
この悲しみにたいする理解は大切だと思います。
またマフィアといえば、ロシアやチャイニーズが有名なわけで、中東にはタリバンがいます。そういった暴力の系譜で、第二地域に勝るところはないかもしれません。
梅棹氏の史観から50年以上がたち、今のボクたちには「すくなくとも(第二地域では)今まで、高度資本主義國になつた例は一つもない」と言えない時代を生きています。
これも引用はしていませんが、「よりよい暮らしを求める」ことが全世界のモチベーションであるという指摘も、その「よりよさ」の内訳に対して、いまの日本人(つーか自分)は迷走しかかっています。
さあ困ったぞ。しかし50年前の梅棹氏はこう言うに留まります。
「サクセションという現象がおこるのは、主體と環境との相互作用の結果がつもりつもつて、まえの生活様式ではおさまりきれなくなつて、つぎの生活様式に移るという現象である。」
ふむ、そうですか。
というわけで、どんなコスモロジーを持つかは、ここでも「てめえで見つける」しかありません。
「日本辺境論」や福田恆存の解析はジュモンのようであり、梅棹忠夫の俯瞰的解剖も、もちろん現状把握という素晴しい武器に違いないが、なにで自分を律するか、どう生きていくかというテーマは、あいかわらず頑として横たわっている。
いや。
もはや「戦後50年 日本人の発言」自体がこのテーマとの格闘の記録である、とも言えるのだ。
最後にこの著書より、引用します。織田作之助「可能性の文学」(1946)。
「日本の文學は日本の伝統的小説の定跡を最高の権威として、敢て文學の可能性を追求しようとはしない。外國の近代小説は「可能性の文學」であり、いふならば、人間の可能性を描き、同時に小説形式の可能性を追求してゐる點で、明確に日本の伝統的小説と區別されるのだ。(中略) 彼等はただ老境に憧れ、年輪的な人間完成、いや、澁くさびた老枯を目標に生活し、そしてその生活の總勘定をありのままに書くことを文學だと思ってゐるのである。彼等の文學のうち、比較的ましな文學の中には彼等がいかに生きて來たかといふことは書かれてゐるだろうが、いかに生くべきかといふ可能性は書かれてゐない」
「彼等」とは、志賀直哉など当時の日本文壇の自然主義作家たちをさしています。
「いかに生きて來たか」。そのフランクシナトラマイウェイ的な慕情は、日本人は大好物です。
しかし「いかに生くべきかといふ可能性」となると、急にドギーマギー、自分の外部に答えを求め、キョロキョロしてしまう。 繰り返すがまさにこの病との格闘が、日本が抱える裏の最大級のテーマなのです。
この「可能性の文學」(青空文庫でも読めます)の最後のほうで、織田は例としてフランスの哲学者で小説家のJ・P・サルトルの「水いらず」を出します。そうした海外文學を引き合いに、(日本の自然主義的)貧血少年が描くムードや雰囲気の裸体ではなく、しっかりと裸体をデッサンすることが肝要で、しかもそれは足がかりに過ぎず、そのデッサンの基礎をもってはじめて、飛躍できる。文學の可能性を探ることができるのだ、と織田は言います。
この結論は美しく、正しい。ボクはこれ以上言うことができません。
こんな格闘を眺めため息をつき、ボクは織田の言うサルトルの「水いらず」が読みたくなりました。
で、2メートル奥の棺に向かいました。
ムフフーン。しってる、知ってる。
あるよ、あるんだよ。 ほら、あったよこれ。
J・P・サルトル「水いらず」(1938)
読んだのは、予備校時代。だからほとんど20年近く前です。
「嘔吐」的雰囲気に憧れていた。 しかし内容はこれっぽっちも覚えていない。
「あまり面白くなかった」という微かな印象すら残っていない。それ以来ひっそりと、置き本となっているわけです。さっそく読み始めました。
読了。 感動。
織田作之助の傍にいたから、すっかり昭和21年の感覚で触れたのだろうか。
あっらー・・こんなにシャープな話だっけ・・
これ当時としては新しすぎないか?
と新鮮な悦びに包まれてしまいました。 リュリュとアンリー、リレットにピエール。
彼女たちは現代も脈々と生きている。 未解決だが、脈々と生きているのです。
さて。
今回の置き本をめぐる旅はそろそろおしまい。
また、どこかで置き本は光り輝くでしょう。
それまでひっそりと本棚で出番を待つ本があるばかりです。